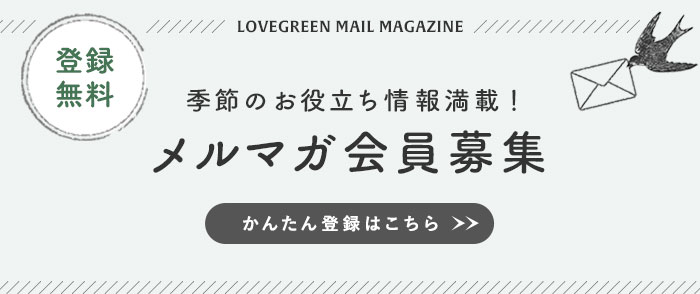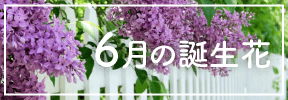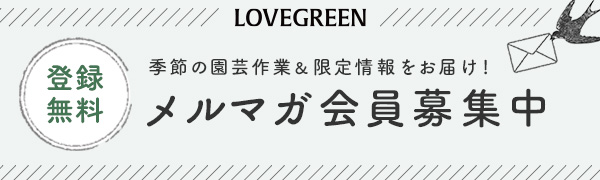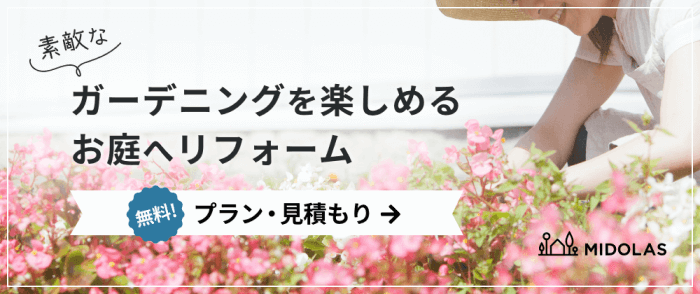和のハーブとは?身近な薬味から薬草まで27種。種類や利用法、料理など
山田智美
このライターの記事一覧

和のハーブって何?どんな種類があるの?そんな疑問にお答えします。種類、利用法や楽しみ方、料理、ハーブティーなど。和のハーブについて詳しく紹介します。
目次
和のハーブとは?

和のハーブとは、古来より日本で親しまれてきた薬草や香草のことです。
ハーブ(herb)とは、薬草や香草のことを指す英語。薬用や食用、香りなど、人間にとって有用な植物を総称してハーブと呼びます。
ハーブとカタカナで書くと西洋のイメージが強くなりますが、日本でも古来より様々なハーブを生活に取り入れてきました。
例えば、1月7日に食べる七草粥は、冬の寒さを乗り越えて出てきた新芽を体内に取り入れることで、邪気を払い、健康を祈願するためのものです。
10月10日の重陽の節句には菊酒を飲み、菊の香りを身にまとって、長寿を祈願したといいます。
今でも薬味として大葉やショウガを用いたり、体を温めるために葛湯を飲んだりと、和のハーブは私たちの生活と密接な関係にあります。
和のハーブの種類27種
和のハーブと言われるものを紹介します。こんなものまで、というような身近な植物ばかりです。
浅葱(アサツキ)

- 科名・属名:ヒガンバナ科ネギ属
浅葱(アサツキ)は日本原産のネギの仲間。明るいグリーンとネギ特有の香りが魅力です。薬味や料理の彩りとして多用されます。
アサツキ(あさつき・浅葱)
- 現在栽培されている野菜のほとんどは外国原産のもので、日本原産とされる野菜はわずかしか確認されていません。その貴重な日本原産の野菜の一つがアサツキです。アサツキは多年草で冬は浅い休眠期に入りますが、0℃近い低温でも停滞しながらも生育することができます。耐寒性に優れていたために、東北地方のような寒いところで栽培されていました。 冬が過ぎ、春になると活発に生育しだし収穫時期になります。4月下旬にはだんだん生育が衰えだし、5月にかけて花茎が伸び、6月上旬頃にアサツキの花が開花します。開花後は地上部が枯れ、7月には種球(鱗茎)の状態で休眠期に入ります。家庭菜園で栽培するときは、休眠からあける8月中旬から9月上旬頃にアサツキの種球(鱗茎)を植え付けることで、10~11月、3~4月頃に収穫時期を迎えます。
山椒(サンショウ)

- 科名・属名:ミカン科サンショウ属
山椒(サンショウ)はピリリとした風味が特徴のミカン科の落葉低木。葉だけでなく、春には花、初夏には果実まですべて食用になります。ウナギの薬味として有名です。
- 山椒は落葉低木で、雄株と雌株の異なる株があります。 樹高は2m~5m、葉の付け根の対称の位置に鋭い棘があり、葉は長さが5~15㎝位です。小さな葉が奇数になり羽状の形をしていていて、5~13枚のギザギザの葉が対(つい)でついています。葉には特有の柑橘に似た爽やかな香りがあります。 山椒は葉、花、実、木の皮まですべて薬味になり、ピリッと舌がしびれるような独特の辛味があります。 山椒の花は4月~5月頃に黄色の小花が咲き、6月になると緑色の果実が雌株には果実が実り始め、9月~10月に赤く実ります。山椒は雄株には花は咲きますが果実は実りません。 雌株と雄株を別々に植えると実がならず、一緒に植えると果実を実らせます。
大葉(青紫蘇)

- 科名・属名:シソ科シソ属
大葉(青シソ)は爽やかな香りが特徴の一年草。生長が早く、初夏から秋まで次々と収穫できます。こぼれダネでも増えるので、なぜか毎年庭に生えてくるというようなこともあります。
香りの良い葉を薬味にするほか、花の部分は花穂シソ、実は穂シソと言って、同じく薬味に使用します。
シソ(大葉)
- シソ(大葉)は草丈約70~80cm位の日本に昔から生育している植物です。シソ(大葉)の葉は柔らかく、とてもさわやかでよい香りが特徴的です。 シソ(大葉)は一度育つとたくさんの葉が茂り、収穫してもわき芽から次々と葉が生えてきます。こぼれ種でも発芽し、まいた記憶もない場所から生えてきたりもします。 緑色の葉紫蘇は別名大葉とよばれています。葉は緑色の他に赤紫の赤じそがあります。赤じそは梅干しの色付けなどに利用されたり、シソジュースの材料としても使用され鮮やかな赤色が魅力的です。 シソ(大葉)は、中国、ベトナム北部、韓国、日本に分布しています。日本では縄文時代の遺跡からも発掘されていることから、古くからシソ(大葉)が生育していたことが分かります。 中国後漢末期の名医「華佗」が食中毒の治療に使ったことから、蘇りの薬草として世に広められたといわれています。そのことから紫蘇と名付けられたとも伝えられています。
赤紫蘇

- 科名・属名:シソ科シソ属
赤紫蘇はシソ科の一年草。葉の色がグリーンの種類は大葉(青紫蘇)、赤い種類は赤紫蘇と呼ばれます。赤紫蘇は主に梅干しの色付けに使用されます。
生姜(ショウガ)

- 科名・属名:ショウガ科ショウガ属
生姜(ショウガ)は熱帯アジア原産の多年草。食用にするのは主に根の部分です。生姜(ショウガ)は世界中で利用されているハーブです。日本では奈良時代には栽培されていたとされています。
料理の薬味の他、肉料理や魚料理の臭み消し、シロップ、ジンジャーエールなど、楽しみ方は多岐に渡ります。
生姜(ショウガ)
- 生姜(ショウガ)は古くから世界中の暖かい地域で、香辛料や薬用として栽培されてきました。原産地はマレー、インドを中心とする熱帯アジアといわれています。 日本でも、奈良時代には栽培されていたとされる歴史のある植物です。栽培が盛んになるのは江戸時代からで、それ以降生姜(ショウガ)は、魚肉料理の臭み消しや、薬味、ジンジャーエールなどの飲み物にも用いられ、私たちの暮らしに欠かせないものとなっています。生姜(ショウガ)は古代中国で、薬として使用されてきました。漢方では主に根生姜(ネショウガ)の部分が使われています。生の生姜(ショウガ)は、吐き気止めや咳を鎮める作用、胃を丈夫にする作用があるとされており、風邪のひきはじめに飲むと効果があります。乾燥させた生姜(ショウガ)は、胃腸などの内臓を温める作用があり、体を強く元気にしてくれる強壮作用があります。
ミョウガ

- 科名・属名:ショウガ科ハナミョウガ属
ミョウガは日本に自生するショウガ科の多年草。食用にするのは花のつぼみと新芽です。ミョウガはシャキシャキとした食感と独特の風味が特徴です。
ミョウガ(茗荷)
- ミョウガは、中国・朝鮮半島・日本・台湾に自生する宿根性の多年草です。日本でも本州から沖縄まで自生しています。地下茎を伸ばして生長します。ミョウガは半日陰と湿った土壌を好みます。地下茎は低温に耐えるため、秋には根に栄養をため休眠期間に入ります。 ミョウガの蕾を食べる「花ミョウガ」と、植え付けてから2~3年たったミョウガの新芽を遮光して軟白化した幼茎「ミョウガ茸」を食べます。 独特な香りをもつ香味野菜。先端の紅色が鮮やかで、ふっくらしたものが良質です。 東京の地名で「茗荷谷(みょうがだに)」がありますが、かつてその場所がミョウガの産地だったことが由来です。切り立った崖の下に清水がわき、周囲でミョウガがたくさん採れたことが分かる文献や地図が残されています。
わさび(山葵)
- 科名・属名:アブラナ科ワサビ属
わさび(山葵)は日本原産のアブラナ科の多年草。葉茎や根茎を食用にします。鼻にツンとくる風味が特徴です。昔からわさび(山葵)には殺菌力があるとされ、刺身の薬味として使用されてきました。
わさび(山葵)
- わさびは北海道から九州の山野に自生している日本原産といわれている植物です。 日本人は、古くから自生しているわさびを採取して使用していました。 わさびはアブラナ科の多年草で、春に芽を出し葉茎が伸びて、初夏に開花し、実を付けます。夏の高温期生長が衰え、秋に再度茎葉が生育して根茎が肥大し、冬に生育が止まる。このサイクルを繰り返しながら、年々根茎を肥大させていきます。わさびの栽培方法は、「沢わさび」と「畑わさび」と育てる場所によってわさびの状態が違います。 沢わさびは根茎がしっかり肥大しますが、畑わさびの方は根茎の肥大が少ないため、葉や茎を食する葉わさびとして野菜感覚で収穫されます。(こちらの育て方では、主に畑わさびの作り方をご紹介します。) 畑でわさびを栽培する場合は、1年目の秋に苗を植え、3年目の初夏に収穫するという長い間かけて栽培します。 このわさびの栽培で大切なのは、強い日差しを避けることです。木漏れ日程度の光と、気温は30℃以下にとどめます。涼しく、光が差し込む程度で湿り気があっても、排水性に優れた環境を好むのがわさびの特性です。 わさびを使う料理の代表格として寿司や刺身が有名ですが、わさびのピリリとした辛みがお醤油と共に魚の旨味を際立たせます。味だけでなく、わさびは強い殺菌力があることでもよく知られています。このわさびの強い殺菌力のおかげで生魚の腐敗を防ぐ効果があるのです。
フキ

- 科名・属名:キク科フキ属
フキは日本原産のキク科の多年草。日本の山野に自生しています。食用にするのは葉柄(ようへい)の部分です。初春に姿を見せるフキノトウはフキの花のつぼみです。フキノトウは春の味覚として人気の山菜です。
ふき(蕗・フキ)
- ふき(蕗・フキ)は数少ない日本原産の山菜で、日本全国の山野に自生しています。キク科フキ属の宿根草で、毎年同じ場所で収穫を楽しめる山菜です。 細長い地下茎を数本伸ばして、その先に大型の葉が発生します。私たちがいつも食べている部分はじつは茎ではなく、葉柄(ようへい)といって茎につながる柄(え)のような部分です。ふきの地下茎は有毒なため食さないように気を付けましょう。 早春の雪解けとともに葉よりも先に花茎が土から顔を出すフキノトウは、ふき(蕗・フキ)の花です。フキノトウは雌花と雄花に分かれています。雄花は黄色で、花が咲き終わると枯れていきますが、雌花は白い花を咲かせた後、茎が伸びタンポポの綿毛のような種子を飛ばします。 北海道の足寄町に自生するラワンブキは、高さ2~3mにも達する大きさが有名で、人気の観光スポットにもなっています。
ヨモギ

- 科名・属名:キク科ヨモギ属
ヨモギは日本の河原や野原に自生するキク科の多年草。昔から春に新芽を摘んでヨモギ餅にするほか、天ぷらやお浸しなど、食用にされてきました。また、お灸のもぐさや、薬用酒などにも使用される、日本の万能ハーブです。
蓼(タデ)
- 科名・属名:タデ科タデ属
蓼(タデ)は独特の香りと辛味が特徴のタデ科の多年草。鮎の塩焼きに添える蓼酢の原料として有名です。
ウイキョウ

- 科名・属名:セリ科ウイキョウ属
ウイキョウは別名フェンネルとも呼ばれるセリ科の多年草。糸状に裂けた明るいグリーンの葉と、全草に甘い独特な香りを持つハーブです。ウイキョウは葉茎、花、果実まですべてが食用になります。果実を乾燥させたものが生薬の茴香(ウイキョウ)です。
ハハコグサ

- 科名・属名:キク科ハハコグサ属
ハハコグサは春に黄色の小さな花を咲かせるキク科の越年草。別名をゴギョウ(御形)と言い、春の七草に数えられます。昔は草餅に入れるのはヨモギではなく、このハハコグサだったそうです。
ナズナ

- 科名・属名:アブラナ科ナズナ属
ナズナは春に小さな白い花を咲かせるアブラナ科の越年草。春の七草の一つとしても有名です。1月7日に七草粥を食べて万病を防ぐという風習は平安時代からあったとされています。
ドクダミ

- 科名・属名:ドクダミ科ドクダミ属
ドクダミは全草に独特の臭いを持った多年草。名前の由来は、毒や痛みを取るという意味の「毒痛み」がなまったという説、毒を全草に溜め込んでいるから「毒溜め」がなまってドクダミになったという説もあります。毒矯めはドクダメと読み、毒を抑える薬草という意味です。
名前の由来には諸説ありますが、ドクダミは薬草として重宝されている植物です。毒があるどころか10の効果があると言われ「十薬」という異名も持ちます。
ドクダミ
- ドクダミは、原産地が東アジアのドクダミ科での多年草です。独特な匂いでコンクリートの割れ目からも生えてくるくらい強く、抜いても抜いても生えてくる……と、雑草扱いされることも多い草花ですが、化学薬品のなかった昔は民間治療薬として重宝されてきた和のハーブのひとつです。 ドクダミは別名「十役」と呼ばれ、開花時期は5~6月で、茎先に十字型の白い花を咲かせます。ドクダミの花名の由来は、毒や傷みを抑える効果を持つことから「毒痛み」が転じたと言われる説と、葉の特有の匂いが毒ではないかといわれたことで「ドクダメ」と呼ばれるようになり、それが「ドクダミ」になったという説があります。 冬の間は地上部分はなく、春になると芽吹いて、花は5月の終わりから6月に開花します。ドクダミの花びらに見える白い部分は「総苞(そうほう)」です。花はとんがっている黄色い部分に密集しています。
スイカズラ

スイカズラは日本の山野に自生するつる植物。学名はLonicera japonica、日本原産です。花には甘い蜜と芳香があるのが特徴です。スイカズラの花色は白から黄色へと変化していくので金銀花という別名もあります。花を乾燥させたものはお茶や生薬として利用されます。
スイカズラ(ハニーサックル)
- スイカズラ(ハニーサックル)は英名をHoneysuckle(ハニーサックル)とも言い、春に香りの良い花を咲かせる半落葉性つる植物です。 スイカズラ(ハニーサックル)の花は、咲き始めは白、次第に黄色と変化します。色が変化するので1本の株に白花と黄花が咲いているようにみえることから、「金銀花」という別名を持ちます。また、冬も緑の葉を絶やさないので「忍冬(ニントウ)」という別名もあります。 スイカズラ(ハニーサックル)は花の蜜を吸うと甘いことから「吸葛(すいかずら)」という名前が付きました。花の形が特徴的で、上下に大きく分かれた花びらの真ん中から雌しべと雄しべが飛び出すように付いています。日本原産の植物ですがヨーロッパで品種改良され、香りの良さから人気が出た植物です。非常に繁殖力が強いため、一部の国では害草として指定されています。 丸みを帯びた卵型の葉が茎に対し二枚両側に付き、葉の付け根から花が咲きます。花後2つの小さな実が付きます。夏の間は濃いグリーンをしていて、熟すと光沢のある黒に変化します。
菊(キク)

- 科名・属名:キク科キク属
菊(キク)は中国原産の多年草。昔の中国では不老不死の薬草と信じられ、重陽の節句には屋外で菊酒を飲み、災いを退けたり不老不死を願ったりしていたそうです。その習慣が日本にも伝わり、重陽の節句に菊酒を飲み、菊を包んだ綿や菊の香りを染み込ませた布で体を拭くなどして、若返りを祈願するようになったと言われています。
キク(菊)
- キクは皇室の紋にも使われている日本を象徴する花のひとつです。中国から奈良時代に伝わり、江戸時代に入ってから盛んに品種改良されるようになりました。こうしたキクを「古典菊」と呼び、「江戸菊」「嵯峨菊」「美濃菊」など地名を冠してカテゴリー分けされています。スプレーギク、ピンポンマムなど、イギリスを中心に欧米で生み出された小輪でたくさんの花をつけるキクは「洋菊」と呼ばれています。花弁の形状は様々。伝統的な白、黄色にはじまり赤、ピンク、オレンジ、複数の色を合わせたものなど数多くの品種があります。古典菊、洋菊どちらも丈夫で育てやすいのが特長。品評会を目指すもよし、色とりどりの寄せ植えにしてもよし、様々な楽しみ方ができます。
藤袴(フジバカマ)

- 科名・属名:キク科ヒヨドリバナ属
藤袴(フジバカマ)は秋に薄紫色の花を咲かせる多年草。遠い昔に薬草として中国から渡ってきたとされています。葉に桜餅を思わせるような芳香があるのが特徴です。
藤袴(フジバカマ)の香りには邪気を払う力があると信じられ、昔の日本の貴族たちは乾燥させたフジバカマの葉を着物に忍ばせて香りを身にまとったそうです。
スギナ(ツクシ)

- 科名・属名:トクサ科トクサ属
スギナ(ツクシ)はトクサ科の多年草。ツクシはスギナの地下茎から出てくる胞子茎です。春に顔を出すツクシはお浸しやキンピラにして食用にします。スギナは乾燥させてお茶や生薬の問荊(もんけい)にされます。
スギナ(つくし、土筆)
- 春になると地面から顔を出すつくし(土筆)はスギナという植物の胞子茎(胞子穂)です。スギナはトクサ科トクサ属のシダ植物です。 つくし(土筆)は春先3~4月頃、まだグリーンが少ない野原や河原の斜面などに顔を出します。スギナとつくし(土筆)は地下茎で繋がっていて、スギナは光合成をする役割、つくし(土筆)は胞子を飛ばす役割を担っています。 つくし(土筆)は筆を逆さに地面に挿したような形状で、ベージュに近い色をしています。節には焦げ茶色の袴(ハカマ)が付いています。つくし(土筆)は春に地下茎から伸びてきて、胞子を飛ばすと枯れていきます。スギナはつくし(土筆)より少し遅れて出てきて、夏が終わる頃まで旺盛に生育し繁茂します。その後、秋には枯れて翌春また出てきます。 スギナはシダ植物なので花は咲きません。つくし(土筆)はスギナの花のような存在とも言えます。他にも「つくし(土筆)」は春の季語とされており、つくし(土筆)は春の味覚として昔から楽しまれています。
クサノオウ

- 科名・属名:ケシ科クサノオウ属
クサノオウはケシ科の越年草。初夏に黄色のかわいらしい花を咲かせます。昔はクサノオウの茎を折ると出てくる黄色い液体を止血に使用したと言います。ただし、この液体はアルカロイドを含んでいるので間違っても口に入れることのないようにしましょう。クサノオウは乾燥させて白屈菜(はっくつさい)という生薬として利用されます。
クコ

- 科名・属名:ナス科クコ属
クコは秋に赤い果実を実らせる落葉低木。クコの実はビタミンB群やCを多く含み、ゴジベリーという別名で美容フードとして人気があります。また乾燥させた葉は枸杞葉(クコヨウ)、根皮は地骨皮(ジコッピ)という生薬にされます。
葛(クズ)

- 科名・属名:マメ科クズ属
葛(クズ)は日本の山野及び街中の公園や空き地などで見かけるつる性の多年草。秋の七草の一つとしても有名です。秋に咲く花にはブドウのような芳香があります。
葛(クズ)の根を掘り上げて外皮を取り、細かくして乾燥させたものを原料としているのが生薬の葛根湯です。また、葛(クズ)の根から抽出したでんぷんは葛粉といってお菓子や料理に使用されます。
ユズ

- 科名・属名:ミカン科ミカン属
ユズは香りが良いのが特徴のミカン科の常緑高木。果皮や果汁を薬味や香りづけに使用します。冬至に入るユズ湯には邪気払い、厄除けなどの意味があるとされています。
柚子(ゆず)
- 柚子(ゆず)は、ミカン科の常緑小高木で、晩秋から冬にかけて鮮やかな黄色の香り高い実をつけます。柚子(ゆず)は、柑橘系では珍しく耐寒温度が-7℃と耐寒性が高いため、風よけや幹の防寒は必要ですが、南東北地方までなら栽培することができます。 柚子(ゆず)の実は、非常に酸味が強く生食向きではありませんが、吸い口や調味料、ジャムとして使われるほか、強い香りで邪を払うということから冬至の柚子湯には欠かせません。 柚子(ゆず)は、栽培も柑橘の中では容易で、自家結実性があるため1本で実をつけます。枝には鋭く長い棘(トゲ)がありますが、近年では棘のない品種も出回っているので、小さいお子さんがいる家庭では棘の少ない柚子(ゆず)を購入されるとよいでしょう。
橙(ダイダイ)

- 科名・属名:ミカン科ミカン属
橙(ダイダイ)はミカン科の常緑高木。橙色の語源にもなっているように、きれいなオレンジ色の果実を実らせます。英名はビターオレンジ。橙(ダイダイ)の名前と「代々」をかけて、正月の縁起物としてお飾りに使用されます。
橙(ダイダイ)の乾燥させた果皮は橙皮(とうひ)、未熟な果実を乾燥させたものは枳実(きじつ)と呼ばれ、生薬にされています。
ムベ

- 科名・属名:アケビ科ムベ属
ムベはアケビ科のつる性常緑木本。アケビと違い常緑で、果実は割れません。その昔は不老長寿の果実と言われていました。
果実は甘く食用にされます。茎や根を乾燥させたものは野木瓜(ヤモクカ)という生薬になります。
ニワトコ

- 科名・属名:ガマズミ(レンプクソウ)科ニワトコ属
ニワトコは日本の山野に自生する落葉低木。春に白い花を咲かせます。エルダーフラワーと呼ばれるのはセイヨウニワトコのことで、ヨーロッパ原産の近縁種です。
ニワトコは花、葉、茎、根まで生薬にされます。それぞれ、接骨木花(せつこつぼくか)、接骨木葉(せつこつぼくよう)、接骨木(せつこつぼく)、接骨木根(せつこつぼくこん)という名前で区別されています。
クロモジ

- 科名・属名:クスノキ科クロモジ属
クロモジは日本の山野に自生する落葉低木。クロモジの枝は爪楊枝の原料にされています。幹や枝に爽やかな香りがあるのが特徴です。クロモジから採れる精油は爽やかで香り高く、和の精油として人気があります。乾燥させたクロモジの枝や幹からはウショウ(烏樟)という生薬が作られます。
- クロモジ(黒文字)は、3月~4月に淡い黄色の小さな花を咲かせる落葉低木です。お茶の席で出される和菓子などに使われる、皮がついたままの爪楊枝は、クロモジ(黒文字)が材料となっています。西日本では、爪楊枝の事を黒文字と呼ぶ地域もあるようです。 クロモジ(黒文字)の名前の由来は、樹皮に黒い斑点があり、その斑点がまるで文字が並んでいるように見えたことからと言われています。 クロモジ(黒文字)の葉や枝には爽やかな香りがあり、お茶として飲用される他、精油(アロマオイル)の原料にもなっています。 クロモジ(黒文字)の楚々とした雰囲気は、和風の庭やナチュラルガーデン、雑木風の庭に相性が良い樹木です。クロモジ(黒文字)の枝は、切り花としても流通していて、生け花やフラワーアレンジの花材としても使われます。派手さはありませんが、若葉、青葉、花、紅葉と見どころのある樹木です。
チャノキ

- 科名・属名:ツバキ科ツバキ属
チャノキは緑茶や紅茶の原料となる常緑低木。葉を摘んでお茶にします。日本では古くから緑茶を嗜好品として楽しんできました。カフェイン、タンニン、フラボノイド、ビタミンCを含みます。
和のハーブの利用法や楽しみ方

薬味や料理の香りづけ
私たちがすでに日々の食生活に取り入れている利用法です。ショウガや大葉、ミョウガなど、香りの良い種類を料理の薬味として使用します。もっとも身近で手軽な利用法です。
香りを楽しむ
ユズや橙(ダイダイ)、フジバカマのような香りの良い植物を乾燥させて、ポプリにして楽しむ利用法です。ふわりと自然な香りが部屋の中に漂います。
お茶にする
好きな和のハーブを乾燥させ、煎じてお茶にするという楽しみ方もあります。
眺めて楽しむ
和のハーブにはスイカズラや菊、フジバカマのような美しい花を咲かせる種類もあります。育てて、観賞して、生活に取り入れてみるのはいかがでしょうか。
和のハーブでチンキ作り
ドクダミなど抗菌作用のある植物を乾燥させて家庭でチンキを作ってみませんか。
▼ドライハーブのチンキの作り方
和のハーブを料理に

和のハーブを料理に取り入れましょう。気軽に楽しめる和のハーブを使ったレシピを紹介します。
しその育て方と塩漬けの作り方
生長が早く、次々と収穫ができるしその楽しみ方です。自宅で育てれば、いつでも薬味に使用できます。まとめて収穫したら、塩漬けにして保存しましょう。
▼和のハーブ!しその育て方と保存法「しその塩漬け」
ポン酢の作り方とポン酢を使った料理
基本のポン酢の作り方と柚子ポン酢の作り方、ポン酢を使った料理レシピまで。香り良いポン酢を自宅で堪能してください。
▼ポン酢の基本や柚子ポン酢の作り方、料理レシピまで!
山うど(山独活)の下ごしらえからおいしい食べ方
山うど(山独活)も和のハーブの一つ。歯ごたえがたまらない山菜です。ここで紹介している下ごしらえや料理レシピは、スーパーで売っているうどにも活用できます。
▼山うど(山独活)のあく抜きや下ごしらえ|美味しい食べ方と栄養
和のハーブティー

ハーブティーとは、植物の葉や茎、花、果実などを煎じた飲み物です。ハーブは乾燥させたもの、あるいはフレッシュのものを使用します。
スイカズラ、ドクダミ、ユズや橙(ダイダイ)の果皮などが和のハーブティーに向いています。
ハーブティーの目安は、ティーカップ1杯分のお湯にティースプーン1杯強のドライハーブです。95~98℃程度のお湯を注ぎ、3~5分蒸らしたら出来上がりです。
▼ハーブティーについて詳しくはこちら
和のハーブとは日本で昔から利用されてきた有用植物のこと。料理、香り、観賞、時には邪気払いや魔除けと、様々な形で私たちの生活に取り入れられてきました。
日本の風土が私たちに与えてくれた恵に目を向けて、見直してみませんか。
▼編集部のおすすめ