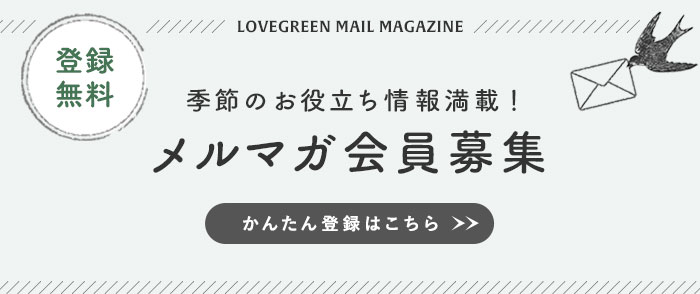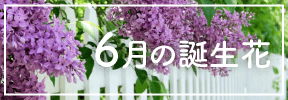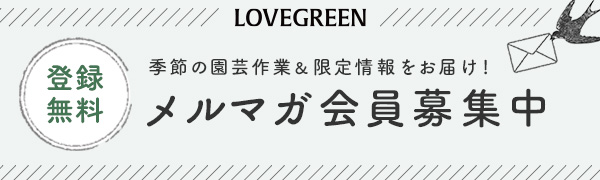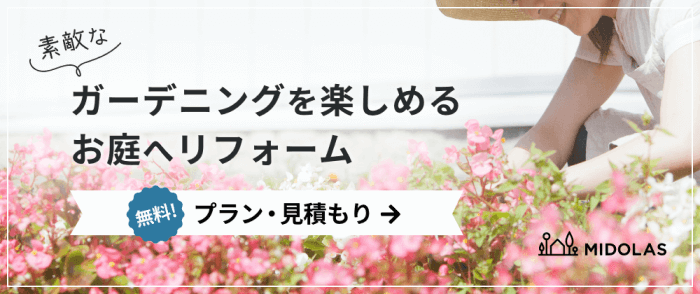初夏っていつ?何月?季語、挨拶、梅雨との違いや初夏を感じる花を紹介
山田智美
このライターの記事一覧

初夏とは具体的にいつなのでしょう。初夏の時期や季語、初夏の挨拶、梅雨との違い、初夏をイメージするもの、初夏に咲く花などを紹介します。
目次
初夏とは。いつ?何月?

初夏とは夏の初め。5月から6月くらいまでのことを指す言葉です。立夏から梅雨入りするまでを初夏ということもあります。
初夏に決められた期間はありません。取り立てて暦の上でいつからいつまでと決まっているわけではなく、陽射しが強くなり、夏を感じるような日が続くようになった頃を表現する言葉です。
初夏に対して晩夏とは?

晩夏とは夏の終わりの頃を指す言葉です。初夏が夏の初めを指すのに対して、夏の終わりを晩夏と呼びます。
晩夏も定められた期間はありません。8月の後半から9月くらいを晩夏と呼びます。
初夏と梅雨の違い

梅雨とは雨季の1種です。春の終わり頃から夏にかけて梅雨前線(ばいうぜんせん)ができ、雨が降ります。
梅雨に入ることを「梅雨入り」、梅雨が明けることを「梅雨明け」と言い、気象台が発表します。
初夏は、まだ真夏ほどの湿気や気温ではないけど、夏を思わせるような汗ばむ陽気と陽射しになってっきたことを表現する言葉です。
初夏と梅雨の違いは、梅雨は気象現象ですが、初夏は肌で感じるものです。
初夏を表す季語や挨拶

初夏に使われる季語を紹介します。
季語とは、俳句などの歌を詠む際に季節を表現するために使用する言葉です。
初夏の季語
- 初夏
- 夏めく
- 薫風
- 余花
- 新緑
- 若楓
- 柿若葉
- 擬宝珠(ギボウシ)
- 麦の秋
- 花橘
- 夏花
- 薄暑
初夏の挨拶
- 「風薫る季節となりました。いかがお過ごしでしょうか」
- 「陽射しが夏めいてまいりました。お変わりはございませんでしょうか」
- 「汗ばむ季節になってまいりました。どうぞお健やかにお過ごしください」
▼初夏の季語を紹介しています。
初夏を感じるものやイメージとは?

初夏は夏の初めの頃。陽射しは強くなり、軽く汗ばむような気温になります。まだ湿気はなく、風が爽やかな季節です。
初夏を感じるものやイメージを紹介します。
- 爽やかな風
- 晴れ渡った青空
- 若葉
- 新緑
- 木漏れ日
- 流れる水
- アジサイの花
- ショウブの花
- サクランボ狩り
- 梅仕事
- 草むしり
- 鮎(アユ)
- 初鰹
初夏に咲く花
アヤメ

- 花期:5月~6月
アヤメは初夏に咲く花の一つです。花の色は紫色か白色。ショウブやカキツバタと似ていますが、外花被片には網目模様があり、なおかつ、つけ根は黄色になっているので見分けがつきます。
ショウブ(花菖蒲)

- 花期: 5月~6月
ショウブ(花菖蒲)は、江戸時代を中心に品種改良が進んだ古典園芸植物です。ムラサキやピンクなど、柔らかく美しい色の花を咲かせます。
ジャーマンアイリス

- 花期:5月~6月
ジャーマンアイリスは、和名「ドイツアヤメ」の他、「レインボーフラワー」、「ヒゲ(ビアデッド)アイリス」といった名前でも知られています。 レインボーフラワーの名は、アイリスの中では最も豊かな色のバリエーションを誇ることからきています。
オダマキ

- 花期:4~7月
オダマキは、北半球の温帯に分布する宿根草で日本にも数種自生しています。オダマキは交配が盛んで、たくさんの園芸品種が存在します。
オダマキ(苧環)
- オダマキ属は北半球の温帯に分布する宿根草で日本にも数種自生しています。オダマキは交配が盛んで、たくさんの園芸品種が存在しています。ここではセイヨウオダマキを含む、オダマキ属について紹介しています。 オダマキは古くから栽培されている多年草で、春から初夏に独特の形の花を俯くように咲かせます。日本に昔から自生するミヤマオダマキは本州中部の高山地帯から北部に分布し、直径3cmほどの青紫色で花弁の先が白色を帯びた花をつけます。同じく日本在来種のヤマオダマキは北海道から九州の山野に自生します。セイヨウオダマキと呼ばれている品種は北ヨーロッパ原産のオダマキの交配種で、花色も紫の他にピンク、白、黄色など花色が豊富です。咲き方も一重咲きから八重咲きや、茎の先に複数輪花を咲かせるタイプまでバリエーション豊富です。
ギボウシ

- 花期:6月~8月
ギボウシは、世界の温帯地域で栽培されている多年草(宿根草)です。日本ではさまざまな野生種が分布し、その生育環境もさまざまです。葉の美しさからオーナメンタルプランツとして人気があり、欧米で交配がなされて多くの品種が作出されました。
クレマチス

- 花期:4月~7月
クレマチスは、日本、ヨーロッパやアジアが原産の多年草。原種は300種類は存在し、日本では「カザグルマ」「ハンショウヅル」「センニンソウ」などがあります。クレマチスは品種によって開花時期も異なり、秋冬に咲くものもあります。
スイカズラ

- 花期: 4月~5月
スイカズラ(ハニーサックル)は、英名をHoneysuckle(ハニーサックル)、あるいはJapanese Honeysuckle(ジャパニーズハニーサックル)、Woodbine(ウッドバイン)と言い、日本からヨーロッパに渡り品種改良がされた植物です。
スイカズラ(ハニーサックル)
- スイカズラ(ハニーサックル)は英名をHoneysuckle(ハニーサックル)とも言い、春に香りの良い花を咲かせる半落葉性つる植物です。 スイカズラ(ハニーサックル)の花は、咲き始めは白、次第に黄色と変化します。色が変化するので1本の株に白花と黄花が咲いているようにみえることから、「金銀花」という別名を持ちます。また、冬も緑の葉を絶やさないので「忍冬(ニントウ)」という別名もあります。 スイカズラ(ハニーサックル)は花の蜜を吸うと甘いことから「吸葛(すいかずら)」という名前が付きました。花の形が特徴的で、上下に大きく分かれた花びらの真ん中から雌しべと雄しべが飛び出すように付いています。日本原産の植物ですがヨーロッパで品種改良され、香りの良さから人気が出た植物です。非常に繁殖力が強いため、一部の国では害草として指定されています。 丸みを帯びた卵型の葉が茎に対し二枚両側に付き、葉の付け根から花が咲きます。花後2つの小さな実が付きます。夏の間は濃いグリーンをしていて、熟すと光沢のある黒に変化します。
マツヨイグサ

- 花期: 6月~8月
マツヨイグサは、6月~8月に明るい黄色の花を咲かせます、花の大きさは3cm程の大きさで、花びらは4枚で夕方から一夜だけ花を咲かせます。花が咲き終わる頃にオレンジ色に花色を変えて、朝になる頃に萎む一夜花です。
ストケシア

- 花期:6月~10月
ストケシアは、初夏から秋にかけて花を咲かせます。薄紫色の大きな花が印象的です。花色は他に白があります。
ドクダミ

- 花期: 5月~6月
ドクダミは、原産地が東アジアのドクダミ科での多年草です。独特な匂いでコンクリートの割れ目からも生えてくるくらい強く、抜いても抜いても生えてくる……と、雑草扱いされることも多い草花ですが、化学薬品のなかった昔は民間治療薬として重宝されてきた和のハーブのひとつです。
ドクダミ
- ドクダミは、原産地が東アジアのドクダミ科での多年草です。独特な匂いでコンクリートの割れ目からも生えてくるくらい強く、抜いても抜いても生えてくる……と、雑草扱いされることも多い草花ですが、化学薬品のなかった昔は民間治療薬として重宝されてきた和のハーブのひとつです。 ドクダミは別名「十役」と呼ばれ、開花時期は5~6月で、茎先に十字型の白い花を咲かせます。ドクダミの花名の由来は、毒や傷みを抑える効果を持つことから「毒痛み」が転じたと言われる説と、葉の特有の匂いが毒ではないかといわれたことで「ドクダメ」と呼ばれるようになり、それが「ドクダミ」になったという説があります。 冬の間は地上部分はなく、春になると芽吹いて、花は5月の終わりから6月に開花します。ドクダミの花びらに見える白い部分は「総苞(そうほう)」です。花はとんがっている黄色い部分に密集しています。
ニゲラ

- 花期:4月~7月
ニゲラは、原産国は地中海沿岸と西アジアの秋まき一年草の草花です。春から初夏にかけて花が咲き、花も葉も独特なフォルムで小さめの花ながら、その雰囲気はとても存在感がある草花です。
ニゲラ
- ニゲラは原産国は地中海沿岸と西アジアの、秋蒔き一年草の草花です。春から初夏にかけて花が咲き、花も葉も独特なフォルムで小さめの花ながら、その雰囲気はとても存在感がある草花です。繊細そうな姿をしていますが、性質は強く、環境が合えば、こぼれ種でも増えます。花びらに見える部分はガク片で、本来の花びらは退化して目立たない形状です。 ニゲラという名はラテン語の「Niger ・黒い」からきています。 和名はクロタネソウと言います、花後にバルーン状の果実が膨らみ、中に黒い種が出来る事からこの名前がつきました。 ニゲラの品種はたくさんあり、年々新品種が作り出されています。園芸店では苗ものとして、生花店では切り花としても流通が増え花以外にも種が入った実の状態でも出回っています。
ニワゼキショウ

- 花期:5月~6月
ニワゼキショウは、北アメリカ原産のアヤメ科の多年草です。夏の暑さに弱いため、一年草として扱われる場合もあります。
ネジバナ

- 花期:5月~8月
ネジバナは、春から夏に芝生や歩道の脇、花壇の中などで咲いているのを見かけるラン科の多年草です。日本に自生する原種のランですが、とても小ぶりであることや生えている場所が他のランとは違うので、雑草として扱われてしまうことがほとんどです。
ノビル

- 花期:5月~6月
ノビルは、春に根を食用にするネギの仲間の野草です。初夏にかわいらしい花を咲かせます。
ハンゲショウ

- 花期:6月~7月
半夏生は、日本、フィリピン、中国の水辺や湿地に自生するドクダミ科の多年草です。ドクダミと同じく地下茎で増えるので、地植えにするとよく広がります。
半夏生(ハンゲショウ)
- 半夏生は、日本、フィリピン、中国の水辺や湿地に自生するドクダミ科の多年草です。ドクダミと同じく地下茎で増えるので、地植えにするとよく広がります。水辺や湿地に自生していることから、湿潤な土を好みます。葉が美しく白くなるには日光も必要なので、日当たりの良い場所~明るめの半日陰くらいの場所で育てるのに向いています。背丈は50cmから1mくらいになる大型の宿根草で冬期は地上部分はなくなります。 半夏生は、6月の終わりから7月初旬にかけて、白い花穂をつけます。開花の頃になると、花穂のすぐ下の葉が半分白くなるのが特徴です。白くなる面積は個体差がありますが、葉が一面白くなることはあまりありません。花が咲くと白くなる理由は、半夏生は虫媒花であるため、葉を白くして虫に花のありかを知らせるためではないかと言われています。 半夏生の名前の由来は諸説あります。夏至から数えて11日目を「半夏生」と呼び、農作業などの目安とされる日でした。この半夏生の頃に花を咲かせるので半夏生と呼ばれるようになったという説があります。また、葉が半分白くなることから、「半化粧」と言われるようになった、という説もあります。学名のSaururusは、ギリシア語のトカゲ=sauros、尾=ouraを意味し、細長い花穂に由来しています。カタシログサという別名は、葉が半分程度白くなることからつけられました。 半夏生の近縁種で、「アメリカハンゲショウ」という品種があります。こちらは開花時も葉が白くなることはありません。
ホタルブクロ

- 花期: 6月~7月
ホタルブクロは中国原産の多年草で、日本でも山野などに自生している植物です。俯くように咲く釣鐘型の花の形が非常に特徴的で可愛らしく、古くから観賞用としても愛されています。この釣鐘型の花の中に蛍が入ると考えられ、ホタルブクロと呼ばれるようになったと言われています。
ヤグルマギク

- 花期:4月~7月
ヤグルマギクは、キク科の一年草。花びらの形は矢車に似ていて放射状に広がっています。ヤグルマギクの花色は白、青、ピンク、紫などがあります。
矢車菊(ヤグルマギク)
- ヤグルマギクは、キク科の一年草。花びらの形は矢車に似ていて放射状に広がっています。ヤグルマギクの花色は白、青、ピンク、紫などがあります。ヤグルマギクの丈は1m位まで生長する高性から矮性種まで様々です。 ヤグルマギクは、以前はヤグルマソウと呼ばれていましたが、別の植物で山間部などに自生しているユキノシタ科の「矢車草」が存在することから、最近はヤグルマギクと呼ばれるようになりました。 ヤグルマギクは、元々雑草でしたが品種改良されてポピュラーな草花の一つになっています。ヤグルマギクの花は乾燥させればドライフラワーにもなるので、生花としてもドライフラワーとしても、楽しむことができる植物です。
ユウゲショウ

- 花期:4月~7月
ユウゲショウは、アカバナ科の多年草です。夕方に咲くことが名前の由来とされていますが、日中から咲いているのを見かけます。
初夏に咲く木の花16種
アジサイ

- 花期:5月~7月
アジサイは、日本の梅雨を代表するような花。梅雨の頃に花の盛りを迎えますが、5月頃から7月の初めごろまで咲いています。涼しげな色が美しい花です。
アナベル

花期:6月~7月
アメリカアジサイやセイヨウアジサイの別名を持つアナベルは、アジサイの仲間の落葉性低木です。花の色は最初はグリーン、咲き進むにしたがって白へと変化します。
エゴノキ

- 花期:5月~6月
エゴノキは、樹高は7~15m前後になる落葉高木。初夏に直径2cmほどの5弁の白い花を鈴なりに咲かせます。
エゴノキ
- エゴノキとは、樹高は7~15m前後になる落葉高木で日本にも広く分布しています。雑木林などにも自生している他、庭木としても親しまれています。樹皮は暗紫褐色でつるんとしてなめらかです。 エゴノキの葉は長さ4~8cmで互生します。5~6月頃に直径2cmほどの5弁の白い花が鈴なりにぶら下がって咲き、独特の美しさがあります。エゴノキの花の散り方は、花びらを散らさずに、咲いていた形のままで落下していきます。白い花がくるくると回りながら落ちていく姿は、とても可愛らしい趣きがあります。秋早めに果実が熟して、1果に1つだけ入っている種を出します。 株立ちのエゴノキは華奢な幹と風が抜けるような涼し気な姿が美しく、シンボルツリーとして人気があります。暑さ、寒さに強い丈夫な樹種で自然樹形のままで整うのも、庭木として人気の理由です。緑陰樹にはなりませんが花が美しいので公園や緑地にも植えられます。ピンクの花が咲く品種もあります。
オリーブ

- 花期:5月~6月
オリーブは、地中海沿岸が原産の常緑高木です。太陽と温暖な気候、水はけの良い土壌を好みます。オリーブは初夏に白や黄白色の小さな可愛い花をたくさん咲かせます。
オリーブ
- オリーブは常緑の高木です。太陽と温暖な気候、水はけの良い土壌とたっぷりの水が大好きです。 オリーブは初夏に白や黄白色の小さな可愛い花をたくさん咲かせます。その様子は同じモクセイ科のキンモクセイとよく似ています。その後、丸くて可愛らしいグリーンの実をつけ、その実は赤、紫、黒へと成熟します。実はそのまま食べるととても渋いのですが、加工することで美味しいオリーブオイルやピクルスなどになります。 そのように家庭の食卓でも日常的に利用されているオリーブですが、植物としてのオリーブの魅力は何といっても樹形と葉の形です。葉の表面は光沢のある緑色、裏面には白い細毛が密生していて、風が吹くときらきらと銀灰色に輝きます。 「平和の象徴」としてハトが葉を口にくわえているデザインをラッキーモチーフなどで見たことがあるかもしれませんが、あの葉はオリーブです。「平和のシンボル」とされるのは「旧約聖書」のノアの箱舟のエピソードに由来します。ハトがくわえてきたオリーブの枝を見て、ノアは洪水が引いたことを知ったのです。 また、オリーブは萌芽力にも優れ、樹齢もとても長く、地中海沿岸地域では1000年を超える老木が今だに実をつけるそうです。 オリーブグリーンと言われる色もありますが、他の植物にはなかなかないような葉色や、スモーキーで乾いた感じの枝や幹の色など、様々な魅力があります。 オリーブは違った品種を2本以上植えた方が実がつく確率が俄然アップします。
カルミア

- 花期: 5月~6月
カルミアは原産地では樹高10mほどになりますが、日本では1m~3mほどにとどまる常緑低木です。つぼみは金平糖のような、チョコレート菓子のアポロに似た形で花が開くと五角形の皿型になります。晩春につぼみが膨らみ、開花期間は初夏から梅雨入りにかけて、約1か月ほどと長期間咲きます。
クチナシ

- 花期:6月~7月
クチナシは常緑低木で、葉は光沢のある長い楕円で濃緑色で、葉脈がはっきりとしています。6月~7月に白色の花を咲かせます。香りが特徴的で甘い香りを周囲に漂わせます。
- クチナシは常緑低木で、葉は光沢のある長い楕円で濃緑色で葉脈がはっきりとしています。クチナシはの花は6月~7月に白色の花を咲かせます。花弁はフェルトのような優しい風合いをしています。香りが特徴的で甘い香りを周囲に漂わせます。 花の形は八重咲と一重咲きがあり、一重咲きの品種は秋になると橙色の実をつけ、熟しても口を開かない事から「クチナシ」の名が付いたと言われています。 お庭に植えられる方も多いクチナシですがだいたい1m~2mにほどになります。枝が詰まって葉が育つ為、垣根としてに好まれます。また、『山吹の 花色衣 主や誰 問へど答へず くちなしにして(秋が過ぎ、冬が来ても一向に口を開けない)』という歌が由来の原点ともいわれています。
サツキ

- 花期:5月~6月
サツキツツジは、「サツキ」の名前でなじみのあるツツジの仲間です。常緑低木で、花も葉も他のツツジより小ぶり。皐月(5月)に一斉に開花することから、この名前が付いたと言われています。
シモツケ

- 花期:5月~6月
シモツケは、バラ科の落葉低木。初夏にピンク色の小花の塊のような花を枝の先に咲かせます。
ジャカランダ

- 花期:5月~6月
ジャカランダは樹高15m以上になるノウゼンカズラ科の落葉高木です。初夏に青紫色の花を咲かせます。葉は鳥の羽のような繊細な形状をしています。
ジャカランダ
- ジャカランダは樹高15m以上になるノウゼンカズラ科の落葉高木です。初夏に青紫色の花を咲かせます。葉は鳥の羽のような繊細な形状をしています。ジャカランダは世界3大花木のひとつとされています。世界三大花木とは、鳳凰木(ほうおうぼく)、火炎木(かえんぼく)ともうひとつが紫雲木(しうんぼく)という和名を持つジャカランダです。 ジャカランダは熱帯地方の乾期に花が咲き、花後か花と同時に新芽を出します。暑さには強く寒さには弱い性質を持っています。ある程度の高木にならないと花が咲かないので、日本ではジャカランダの花の鑑賞は難しいとされてきました。最近では日本国内でも温暖な地方では満開のジャカランダを見られます。 原産地は南米ですが、ポルトガルでは大航海時代に南米から入ってきたものが根付いたと言われており、ポルトガル人にとっても特別な花です。日本人が春の桜を心待ちにするように、ポルトガルでは青紫のジャカランダの花が愛されているそうです。 ジャカランダは温暖な気候を好むため、関東以北の露地では越冬が難しいと考えられています。小さなサイズの鉢植えのジャカランダは、観葉植物として親しまれています。小さな鉢植えのジャカランダは花は咲きませんが、明るいグリーンの葉に観賞価値があります。
スモークツリー

- 花期:6月〜7月
スモークツリーは、初夏になると穂状の花序に小さな黄緑色の花が無数に開花します。羽毛のようなふわふわとした花が特徴的です。
- スモークツリーは、初夏になると穂状の花序に小さな黄色の花が無数に開花します。雌雄異株で、タネを結ばない不稔花である雌木の軸の部分(花柄)が長く伸びて、羽毛のようなふわふわとした触感と見た目になります。雄木の花柄は雌木に比べて小さいので、煙がくすぶっているようには見えません。切り花や庭木として植栽されているのは雌木です。花柄は長いもので20cm以上にもなります。開花後のスモークツリーの花柄が、煙がたっているかのように見えることが名前の由来です。庭木の他、花柄が付いた枝ものとして初夏に多数流通しています。 スモークツリーは花柄だけでなく、葉も魅力的で、紅葉も美しい樹木。暑さ寒さにも強く、手入れが簡単なこともあり、おしゃれな庭木として人気です。ウルシ科のため、剪定した際の切り口に素手で触れるとかぶれることがあります。ヤニもあるので、作業で触る際には手袋をするようにしましょう。
セアノサス

- 花期:4月~6月
セアノサスは、青紫色の鮮やかな花が美しい花木。カリフォルニアライラックという名前でも流通しています。
タイサンボク

- 花期:5月~7月
タイサンボクは、樹高が20mにもなるモクレン科の常緑高木です。初夏に白く大きな花を咲かせますが、上の方の枝に花が付くので、下から見上げても気付かないことが多いくらいです。直径20cm以上はある大きな花で芳香があります。
泰山木(タイサンボク)
- 泰山木(タイサンボク)は、樹高が20mにもなるモクレン科の常緑高木です。初夏に白く大きな花を咲かせますが、上の方の枝に花が付くので、下から見上げても気付かないことが多いくらいです。花は直径20cm以上はある大きな花で芳香があります。 香水の原料や化粧品の香料として「マグノリア」と言われる場合は泰山木(タイサンボク)のことを指します。マグノリアとは、モクレン( Magnoliaceae)科モクレン( Magnolia)属の植物の総称です。モクレンやコブシ、泰山木(タイサンボク)、オオヤマレンゲなど全て含まれます。泰山木(タイサンボク)は中でも香りが良い為、香料とし利用されます。 泰山木(タイサンボク)は葉の表面がツルツルとしていて光沢があるのが特徴です。反面葉の裏側は茶色く、少し毛羽立ったような手触りが特徴です。クリスマス時期になると出回るマグノリアのリースやマグノリアボールなどは、この泰山木(タイサンボク)の葉を使って作られています。
テイカカズラ

- 花期:5月~6月
テイカカズラは、5月~6月頃、直径2cm程度の芳香のある花をたわわに咲かせます。全体がクリーム色で中心に近づくにつれて黄色が強くなる花は、プルメリアを小ぶりにしたようで、南国を思わせる雰囲気があります。
- テイカカズラは、日本原産のつる性常緑低木です。テイカカズラの名前は、能楽「定家」が由来とされています。式子内親王と藤原定家の悲恋の物語です。式子内親王へ恋焦がれた藤原定家は彼女の死後、テイカカズラとなってその墓にまとわりつき墓石を覆ってしまったと言われています。 テイカカズラは初夏、5~6月頃、直径2cm程度の芳香のある花をたわわに咲かせます。全体がクリーム色で中心に近づくにつれて黄色が強くなる花は、プルメリアを小ぶりにしたようで南国を思わせる雰囲気があります。 葉は光沢のある明るいグリーンで、茎の途中からも気根を出して塀や他の樹木に張り付くように伸びていきます。仲間にハツユキカズラという、葉を観賞する目的で作られた園芸種もあります。 キョウチクトウ科は有毒物質を含むと言われていますので、口に入れることの無いように注意してください。また樹液で肌がかぶれることもあるので、触れるときは気を付けるようにしましょう。
ハコネウツギ

- 花期:5月~6月
ハコネウツギは、初夏に白とピンクの花を咲かせる落葉低木です。アジサイに似た葉と漏斗状の花が印象的です。
ヒメシャラ

- 花期:6月~7月
ヒメシャラは、6月~7月頃、ツバキに似た花(花径2~2.5cmほど)を咲かせます。花芯部が黄色で白い花びらをもつ、コントラストが美しい花です。樹高は10~15mにもなる落葉高木です。
- ヒメシャラは6月~7月頃、ツバキに似た花(花径2~2.5cmほど)を咲かせます。花芯部が黄色で白い花びらをもつ、コントラストが美しい花です。樹高は10~15mにもなる落葉高木です。シャラノキ(ナツツバキ)によく似ていますが、花も葉もシャラノキ(ナツツバキ)より小さい特徴があります。ちなみに、シャラノキ(ナツツバキ)の花径は5~6cmほどです。ヒメシャラ(姫沙羅)という名は、シャラノキ(ナツツバキ)よりも小さな花が咲くことから付けられました。 ヒメシャラは日本の本州(関東地方より南)、四国、九州の山野などに自生しています。秋には紅葉が美しく、落葉後も赤褐色の太い幹がツヤツヤと輝き、樹形もきれいで観賞価値が高いことから庭木やシンボルツリーとしても人気があります。
ムラサキシキブ(紫式部)

- 花期: 6月
ムラサキシキブ(紫式部)は、秋に紫色の果実を実らせる落葉低木です。初夏に小さなピンク色の花を咲かせます。ムラサキシキブ(紫式部)の花だと気づかずに見逃してしまうことも多いようです。
- ムラサキシキブ(紫式部)は、秋の紫の実が美しい日本原産の落葉低木です。古くから山地の湿地や森林に自生しています。葉の色は実がなりだす初秋の緑から、秋が深まってくると黄色く紅葉し、紫色の実との色合いがとても美しい光景で、英名ではJapanese beautyberryとも言われています。実は葉が落葉した後もしばらくついていますが、冬に自然に落下します。 ムラサキシキブ(紫式部)の近縁にコムラサキがあり、流通上はコムラサキも含めてムラサキシキブ(紫式部)として販売されていることが多く、園芸店で販売されているムラサキシキブ(紫式部)はコムラサキであることの方が多いため、個人宅や公園などの公共スペースの植栽で見られるのはコムラサキです。それぞれは樹高や実の付き方に違いがありますが(下記参照)、育て方に違いはありません。 コムラサキの園芸種でシロシキブ(白式部)と言って、実が白の種類もあります。
初夏は一年でもっとも風が心地よい季節と言っても過言ではないと思います。程よく湿度が低く、陽射しは強すぎず過ごしやすい季節。
初夏には新緑のなかで深呼吸しながら、草むらの中で咲く余花を眺め、自然を満喫して過ごしてみませんか。
▼編集部のおすすめ